
秘密保持契約とは、契約当事者間で重要な情報のやり取りが発生する場合に、その情報を外部に漏らさないよう約束する契約のことです。
秘密情報が漏洩した場合にスムーズな損害賠償請求が可能になるなどのメリットがあり、さまざまなビジネスシーンで活用されています。
本コラムでは、秘密保持契約(NDA)についての予備知識や、秘密保持契約書(NDA)を作成する際に必要な条項などについて解説します。
▼この記事でわかること
- 秘密保持契約(NDA)とは何かがわかります
- 秘密保持契約書(NDA)に記載する条項がわかります
▼こんな方におすすめ
- 初めて秘密保持契約書(NDA)を結ぼうとしている方
- 相手方から提示された秘密保持契約書(NDA)について知りたい方
- 秘密情報の漏洩を受け、改めて秘密保持契約書(NDA)の定義や条項について知りたい方
目次
秘密保持契約書(NDA)とは
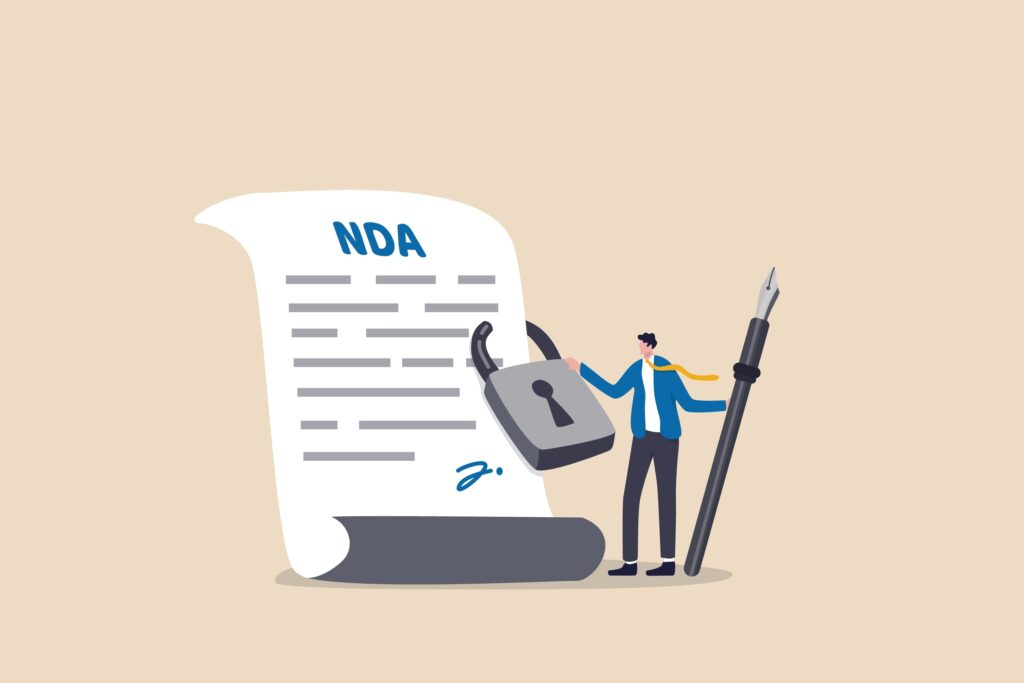
秘密保持契約書(NDA)は、契約のひとつで、契約当事者間で授受される一定の情報を第三者に提供すること等を禁止する旨の契約です。
例えば、自社の情報を開示した上で一定の業務を外注する際に、自社で秘密情報として管理している商品の生産方法、販売方法、顧客情報等の重要な情報の漏洩を防止する目的で締結されます。
英語のNon-Disclosure Agreementを省略して「NDA」と呼ばれています。
秘密保持契約書(NDA)はどういった目的の元、締結されるのでしょうか。
使用シーンや契約締結の特徴を含めて解説します。
秘密情報の流出を防ぐのが目的
秘密保持契約書(NDA)は、自社の秘密情報を相手方が第三者に開示・漏洩するのを防ぐことを主な目的としています。
ビジネスを中心とした取引は、自社と相手方の双方の信頼関係のもとに成り立っています。
しかし、ノウハウや知識といった財産的情報の価値が高まる現代では、財産的情報を悪用する取引先がいないとも限りません。
そうした背景によって、急速に利用が広がってきたのが、秘密保持契約書(NDA)です。
昨今は、情報を無形の知的財産として扱う欧米取引業界の取引慣行が浸透していることもあり、その重要性が高まっています。
取引先や従業員への情報共有の際に利用される
秘密保持契約書(NDA)は一般的に、売買契約や、業務委託契約、サービス利用契約、投資契約等の取引の検討の準備段階として締結されたり、これらの契約を締結するのと同時に締結されます。
例えば、企業が何か取引を始める際に、公然とは知られていない生産方法や販売方法など、事業活動に有用な秘密情報を相互に共有する必要がある場合に用いられます。
この秘密情報を秘密保持契約書(NDA)を締結したうえで共有することで、売買や賃借、請負、委任などの取引のほか、産学で実施する共同研究や、企業の合併、吸収、提携などのM&Aに至るあらゆる交渉が、円滑に進みます。
NDAを締結しないままでは十分な情報のやり取りができず、実質的な契約交渉ができない場合もあります。
また、従業員は、労働契約の存続中は、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務を負っています。
多くの企業では、就業規則などの社内規程で、秘密情報の保持義務がうたわれています。社内規程に加え、又は社内規程に代えて、従業員と秘密保持契約書を締結することもあります。
締結の時期
秘密保持契約書(NDA)は、秘密情報を開示する前に締結します。
具体的には、従業員の雇用など人材登用であれば、入社する前のタイミングで雇用契約書などの個別契約書に秘密保持条項を定めます。
また、第三者との業務提携を行う場面等では、まず、その第三者と業務提携をすることで、お互いが自社にとってメリットが有るか等を検討する必要があります。
もっとも、お互い相手方の情報がなければ検討することができません。
そのため、業務提携契約を締結する前に、そもそも業務提携契約を締結するかどうかを検討するために情報の授受を行うため、そのタイミングで、相手方と秘密保持契約書(NDA)を締結します。
このように秘密情報を開示する前段階で秘密保持契約書(NDA)を結ぶことで、安心して取引関係に入ることができます。
収入印紙は不要
秘密保持契約書(NDA)は原則として課税文書ではないため、収入印紙は不要です。
しかし、秘密保持契約書(NDA)という契約書名であっても、継続的取引に関する事項や業務請負に関する事項が含まれている場合など、課税文書に当たる場合は収入印紙が必要となります。
秘密保持契約書(NDA)の条項

秘密保持契約書(NDA)に契約書に記載する条項の例として下記の12項目を解説します。
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務
- 情報授受の目的と目的外利用の禁止
- 秘密情報の返還・破棄
- 秘密情報の複写・複製
- 契約上の地位の譲渡等の禁止
- 有効期間
- 損害賠償
- 存続条項
- 損害賠償等
- 協議解決
- 専属的合意管轄
ここからは、それぞれの詳しい内容について解説します。
秘密情報の定義
秘密情報という用語に法律上の定義はありませんので、契約書において定義しなければ、何に対して秘密保持義務が発生するのかわからず、意味のない契約になってしまいます。
そこで、当事者間で開示される情報のうち、どのような情報を秘密情報として扱うのかを定義しましょう。
例えば、情報受領者が相手方から開示された一切の情報と広く秘密情報を定義したり、一定の情報に限定する趣旨で、営業上または業務上の情報などと記載することがあります。
また、書面などに「秘密」や「秘」と表示するなど、秘密と明示された情報に限定して定義する場合もあります。
さらに、ある契約の秘密保持条項などで、契約締結の事実や契約自体の存在や内容、契約交渉の経緯や内容などを秘密情報の定義に含ませることもあります。
この旨が記載されている場合、契約当事者は、たとえば、業務提携契約の交渉の内容や、相手方との間でМ&Aの仲介業務委託契約を締結している事自体を第三者に開示することはできません。
また、秘密情報から除外する情報も定義されることが一般的です。
下記の5点が秘密情報から除外されることが一般的です。
- 既に保有していた情報
- 既に公知となっている情報
- 取得後に受領者の帰責事由によらず公知となった情報
- 第三者から適法に入手した情報
- 独自に開発した情報
秘密保持義務
この条項は、秘密保持契約(NDA)の根幹的な規定で、秘密情報を第三者に対して開示・漏洩してはならない旨定められるものです。
この条項では、上記と併せて、第三者の範囲を定義する場合が一般的です。
たとえば、関連会社や委託先、弁護士などの専門家を除き、第三者に秘密情報を開示してはならないなどと、第三者の範囲を限定することで、関連会社等に開示することが可能になります。
また、法令に基づき行政機関などから開示が求められる場合は、必要最小限の範囲で情報を開示できる旨を規定する場合もあります。
情報授受の目的と目的外利用の禁止
秘密保持契約(NDA)では、当事者がなぜ情報の授受を行うのか、その目的を記載します。
それは、どの会社でも重要な情報を開示する際には、その意図があるためです。
開示できるかどうかを検討する際には「相手方が●●のために情報を使いたいのであれば開示しよう」という判断を行っています。
目的を限定せずに何でも使っていい、という場面はあまり想定できません。
例えば、「業務委託の可否を検討するため」「業務提携の可能性を検討するため」などといった文言です。
上記の背景から、情報授受の目的を規定するのと合わせて、その目的外で情報を利用することを禁止する旨を規定します。
情報を授受する目的を明記することで、秘密情報が流用されることを防止することができます。
その他この情報授受の目的は、目的を達成した場合には情報を返還するなど、情報の返還時期や契約の終了時期に関連する場合もあります。
秘密情報の返還・破棄
この条項は、契約が終了した場合や開示者が要求した場合などに開示した秘密情報について、返還義務や破棄義務を相手方に課すための規定です。
これにより、相手方の元に渡った秘密情報が無益に相手方に存在することを防げます。
破棄した際に、破棄証明書の差し入れを義務付ける旨の規定を定める場合もあります。
秘密情報の複写・複製
この条項は、複写・複製した情報も秘密情報に含まれることについて確認する規定です。
秘密情報を複写・複製した場合でも、複写・複製した情報に秘密情報が含まれる場合は、秘密情報として扱われるべきですが、当事者間で認識の相違が生じる可能性があります。注意的に規定することで後のトラブルを防止することができます。
秘密情報を複写・複製してはならない、と定めることもあります。
契約上の地位の譲渡等の禁止
この条項は、秘密保持契約書(NDA)の締結で得た契約上の地位や権利、義務を、相手方の許可を得ずに第三者に譲ることを禁止する規定です。
この条文を明記しておくことで、相手方を信用して秘密保持契約書(NDA)を締結したにもかかわらず、相手方そのものが変わってしまったという事態を防げます。
有効期間
この条項は、秘密保持義務をいつまで負うかを定めた規定です。
本契約締結の日から●年間などと規定するほか、取引関係に入ることを検討する際に締結するNDAでは、検討が終了した時期を終了時期としたり、 取引契約と同時に締結するNDAでは、その取引契約が終了する時期をNDAの終了時期と規定することもあります。
存続条項
この条項は、契約が終了した後も秘密保持義務を維持させることを定めた規定です。
有効期間は契約期間であるのに対し、存続条項は、指定した一部の条項について、契約終了後であるけれど、一定の期間はなお有効として取り扱う条項です。
存続期間については、無制限とすることもありますが、一定の期間に限定することも多いです。どの程度の期間にするかは、情報の重要性や陳腐化のスピードを考慮して定めることになります。
損害賠償等
この条項は、秘密保持義務に違反した場合、賠償責任が生じることを明記した規定です。
損害賠償責任は、事後的な救済措置ですので、合わせて事前の救済措置として秘密情報の使用差し止めを請求できる内容を明記しておくことも重要です。
協議解決
この条項は、秘密保持契約書(NDA)を巡って紛争が生じた場合に、誠意を持って協議して解決することを定めた規定です。
この条項に法的に特別な意味はありませんが、契約当事者の心構えを確認する目的で明記しておくとよいでしょう。
専属的合意管轄
この条項は、訴訟が起きた場合に、第一審に限り、合意によって管轄裁判所を定めることを定めた規定です。
まとめ

秘密保持契約書(NDA)は、取引に伴い発生する秘密情報のやり取りの安全性を保証し、円滑に取引を進めていくうえでは欠かせない契約です。
特に事前交渉段階で、秘密保持契約書(NDA)を締結することで、より深い検討が可能になり、当事者双方の利益の増大が実現できるでしょう。
ただし、秘密保持契約書(NDA)の記載に漏れがあると、秘密情報が漏洩したり、漏洩時に相手から賠償してもらえなくなるといった問題が起きかねません。
秘密保持契約書(NDA)を作成するために、まずは秘密保持契約書(NDA)作成に実績のある弁護士に相談することをおすすめします。

