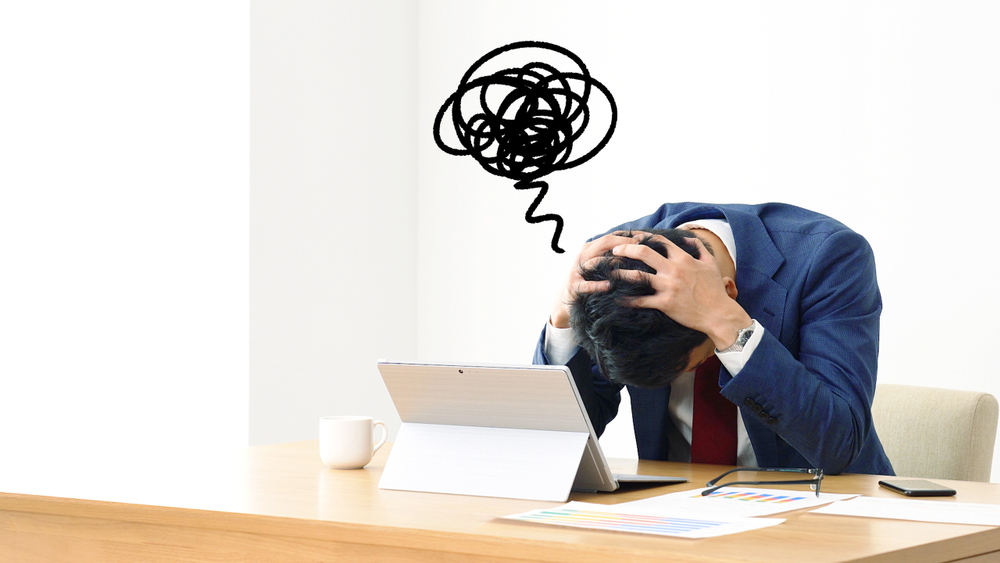無断欠勤を繰り返す社員やスキルが著しく低い社員など、問題社員にお悩みではないでしょうか。
問題社員が自主退職をせず、解雇を検討する場合、日本の法律は労働者を強く保護している点に注意が必要です。
正当な解雇理由を明らかにして適切な手順を踏まなければ、不当解雇となる危険性があります。
この記事では、不当解雇にならないように進める方法を詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 従業員の退職に向けた適切な方法がわかります
- 退職勧奨と解雇のそれぞれの手順を紹介します
- 従業員の退職勧奨、解雇を検討する際に考慮すべきポイントを説明します
こんな方におすすめ
- 辞めてほしい問題社員にお困りの方
- 問題社員を解雇したいけれど不当解雇になりそうで不安な方
- 問題社員を解雇するまでの流れを知りたい方
目次
退職勧奨、解雇について

ある社員の問題行動により、今後自社で働いてもらうことが困難と考えた場合、会社側から行動を起こす場合の選択肢としては「退職勧奨」または「解雇」が考えられます。
さらに、この場合の解雇には、おもに「懲戒解雇」と「普通解雇」の2種類が考えられます(後述しますが、懲戒解雇の適法性は非常に厳格に判断されます)。
退職勧奨
退職勧奨とは、会社が従業員に対して自発的な退職意思形成を促す行為です。
本人の合意を得られた場合、退職届を提出してもらって退職手続きを進めます。
従業員が退職勧奨によって退職した場合、会社都合の退職と考えられます。
本人が退職に同意しないかぎり、会社側が無理に辞めさせることはできません。
退職勧奨はあくまで本人の意思にもとづく退職であり、強制力がないため法律上の厳格な規定はありません。
強制力のある解雇と比べて、ハードルが低い方法と言えます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、企業の秩序を乱した従業員との労働契約を打ち切る解雇方法です。
懲罰的な意味合いが大きく、重大な問題行動を起こした従業員への制裁として行われます。
たとえば、職場での横領などの犯罪行為、悪質なハラスメント行為、度重なる無断欠勤といった行動が該当します。
組織で行われる懲戒処分のなかでもっとも重く、退職金は減額や不支給となる事例が一般的です。
なお、懲戒処分を行うには、就業規則、労働協約等で懲戒処分の根拠となる定めが必要となり、具体的には懲戒の事由、懲戒の種別を定める必要があります。
懲戒の事由(懲戒解雇事由)に該当する事実があっても、懲戒権の濫用にあたれば無効となります(労働契約法15条)。懲戒解雇に関しては上記のとおり非常に重い処分であるため、適法性も厳格に判断されると考えられます。
|
労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、 (参照:e-Gov法令検索「労働契約法」より) |
普通解雇
通常、やむを得ない理由で社員を辞めさせたい場合には普通解雇が選択されます。
具体的には、能力不足や職務怠慢、協調性の欠如、傷病により休職したが復職できない状態などのケースが当てはまります。
懲戒解雇と異なり、普通解雇は就業規則に記載のない理由でも行えると解されていますが、労働契約法第16条に違反しない場合(解雇に客観的合理的な理由があり、社会通念上相当であること)に限られます。
|
労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (参照:e-Gov法令検索「労働契約法」より) |
解雇のハードルが高い理由

もっともスムーズな退職に向けた対応は退職勧奨ですが、すべての人が退職に合意してくれるわけではありません。
従業員が退職に応じない場合、解雇をすれば問題ないのでしょうか。
現実的には、次の3つの理由により解雇のハードルは高くなっています。
労働契約法による労働者の権利保護
すべての労働者は、労働契約法によって固く保護されています。
前述した労働契約法第15条、第16条では、懲戒処分や解雇の制限について規定しています。
|
労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、 (参照:e-Gov法令検索「労働契約法」より) |
|
労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (参照:e-Gov法令検索「労働契約法」より) |
したがって、普通解雇や懲戒解雇であっても、客観的に合理的な理由がない場合や社会的相当性がない場合は認められません。
注意点として、会社側が解雇相当だと判断しても、裁判で無効とされるケースが珍しくありません。
たとえば、営業活動の虚偽報告をした社員を懲戒解雇した事例では、懲戒解雇は不当とする判決が出されています(東京地裁2017年10月27日判決)。
裁判所は労働者の解雇を慎重に判断するため、どのような問題社員でも解雇の正当性を検証する必要があります。
不当解雇のリスク
不当解雇のリスクの高さから、なかなか解雇に踏み切れない企業は多いです。
裁判によって不当解雇と見なされると、「バックペイ」の支払い義務が生じます。
バックペイとは、解雇が無効になった際に支払う賃金です。
会社は、不当解雇した日以降の未払い分を支払わなくてはいけません。
また、不当解雇による企業イメージの低下も深刻です。
社会的な信用を損ない、新たな人材確保の妨げとなりかねません。
不当解雇と判定された場合のリスクの多さにより、問題社員の解雇を断念するケースがよくあります。
裁判にかかる労力やコスト
不当解雇によるリスクに加えて、解雇者による裁判への各種リソースを想定して解雇を躊躇するパターンもあります。
訴訟や労働審判で争い、解雇の正当性を認めてもらうためには多くの費用や手間、時間が必要です。
裁判に時間やコストをかける余裕がない企業にとって、問題社員を解雇するハードルはより一層高くなるでしょう。
問題社員への対応にあたって考慮すべきポイント

問題社員への退職勧奨や解雇を検討する前に、次の4つのポイントを確認しましょう。
異動により解決できる可能性の有無
問題社員を異動させることによって解決できる可能性があります。
現在のポジションが本人の適性と合っておらず、能力を発揮できていないかもしれません。
また、コミュニケーション上の問題がある場合、現在の部署やチームのメンバーと相性が悪いだけのパターンも考えられます。
まずは本人の希望や悩みをヒアリングして、人事異動を検討してみてください。
本人への指導内容の確認
問題社員への指導内容をあらためて確認しましょう。
本人へ問題点をはっきりと伝えていない場合、行動を改善させることは困難です。
伝えづらい内容でも具体的に問題点を伝えて、改善策を指導しましょう。
さらに、問題点をきちんと指摘していても、指導内容の方向性が的確でない可能性もあります。
指導内容を再検討して、本人へ行動の改善を促しましょう。
段階的に解雇へ進める
問題社員の解雇を決断しても、いきなり解雇することは難しいです。
一般的に、裁判所は解雇の正当性を判断する際、解雇の過程も考慮します。
まずは注意・指導を行ってから、指導に従わない場合に懲戒処分を実行しましょう。
複数回の懲戒処分でも改善が見られない場合、退職勧奨、解雇へと進みやすくなります。
段階的に解雇へ移行することで、万一の裁判でも不当解雇と見なされる一因を回避できます。
違法な手段で退職へ追い込まない
問題社員を辞めさせたいあまり、以下のような方法で退職へ追い込むことはおすすめできません。
- 嫌がらせ目的で異動させる
- プロジェクトから外す
- 仕事を取り上げる
- 業務上のノルマを釣り上げる
- 侮辱する・怒鳴りつける
- 「辞めないと懲戒解雇する」と脅迫する
こうした手段により問題社員が退職したとしても、不当解雇のみならず慰謝料を求めて訴訟を起こされるリスクが生じます。
違法な手段に頼らず、法律を順守したうえで退職勧奨や解雇を実行しましょう。
問題社員の退職へ向けた流れ|退職勧奨

問題社員に退職してほしい場合、はじめから解雇するのではなく退職勧奨から着手しましょう。
退職勧奨は、以下5つの手順で進めます。
1.現状調査
まずは、問題社員について現状を調査します。
具体的な問題の内容やこれまでの対応履歴を確かめましょう。
適切に事実確認を行うことで退職を求める理由が明確になり、本人に退職を納得してもらいやすくなります。
また、不当な懲戒処分を行ったり、誤った状況によって解雇したりする事態も避けられます。
2.再度の注意・指導
調査内容をもとに、あらためて注意や指導を行います。
不十分な指導のまま退職勧奨をした場合、本人は問題点の自覚が薄く退職を受け入れづらいでしょう。
さらに、問題社員を解雇する場合にも注意や指導の実績が重要です。
不当解雇の判例では、不十分な注意や指導を理由として解雇が無効とされた事例が多数あります。
万一の訴訟を見据えて、注意・指導の実績を重ねて文書化しておきましょう。
3.就業規則の確認
当該社員の抱える問題が、就業規則のどの項目に該当するのかを確認します。
就業規則に規定されていない理由で退職勧奨を申し出ても、納得してもらえる可能性は低いです。
解雇へ進んだ場合も、就業規則にない理由による解雇は不当と見なされるリスクが高まります。
退職勧奨の段階で就業規則を確認しておくことで、仮に解雇が必要になってもスムーズに手続きを遂行できます。
4.懲戒処分の検討・実施
必要に応じて、懲戒解雇よりも軽微な処分を検討・実施します。
できる限り、もっとも軽い処分の「戒告・けん責」から行いましょう。
懲戒処分によって本人の意識が改められれば、退職勧奨を行う必要がなくなります。
懲戒処分を実行する際は、問題行動に対して重すぎる処分にならないよう注意が必要です。
懲戒処分後も問題行動が改善されない場合、一段階重い処分を検討しましょう。
また、注意・指導の実績と同じく、懲戒処分の実績も解雇後の訴訟で有利に働きます。
5.退職勧奨の実行
度重なる注意・指導や懲戒処分を行っても本人に改善が見られない場合、退職勧奨に移行します。
本人と個別に面談して、退職してほしい旨と具体的な理由を伝えます。
「退職を強要された」と主張されるトラブルを避けるため、可能であれば本人の了承を得て録音しましょう。
回答はその場で求めずに再度面談日を設定することで、本人も冷静に決断できます。
退職の合意を得られたら、退職日や退職金について本人と相談して決定します。
問題社員の退職へ向けた流れ|解雇

問題社員が退職勧奨に応じなかった場合、直ちに従業員を辞めさせたいと考える場合は、解雇に進むほかありません。
従業員を解雇する際は、次の5つの手順に沿って着手しましょう。
1.解雇制限期間の確認
はじめに、対象の社員が以下の「解雇制限期間」に該当しないかを確認します。
- 労災による休業期間とその後30日間
- 産休期間とその後30日間
上記のどちらかに該当する場合、問題社員は解雇できません。
ただし、該当する場合であっても、打切補償(1200日分の平均賃金)を支払えば解雇が可能です。
2.解雇理由の整理と関係者への共有
解雇する理由をまとめ、あらためて就業規則と照らし合わせて解雇の正当性を確認します。
加えて、当該社員の直属の上司や経営上層部などの関係者へ、解雇に関する情報を共有しましょう。
早い段階で関係者の理解を得ておくと、突然関係者から解雇に反対される心配がありません。
3.解雇方法の選択
解雇を決定したら、普通解雇または懲戒解雇のどちらかを選択します。
能力不足や協調性の欠如、復職が不可能な傷病を理由とする場合、普通解雇が一般的です。
横領や経歴詐称などの不正行為、無断欠勤、ハラスメント行為(程度によります)といった就業規則に規定された行動が原因の場合、懲戒解雇の方針で進めることも選択肢です。
なお、懲戒解雇は退職金の減額などの不利益が労働者に生じるため、裁判では普通解雇よりも厳格な判断がされる傾向にあります。
そのため、懲戒解雇に相当する状況であっても、普通解雇を選択したほうが良いケースも存在します。
4.解雇予告通知書の作成
問題社員へ解雇を通達する「解雇予告通知書」を作成します。
社員を解雇する際は、解雇日の30日前までの予告が義務づけられています。
|
労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 (参照:e-Gov法令検索「労働契約法」より) |
解雇を予告せず即日解雇する場合、「解雇通知書」を交付して30日分以上の平均賃金を支払います。
5.本人への解雇予告通知
問題社員へ解雇予告書を提示して、解雇の予告を伝えましょう。
個別に本人を呼び出して、解雇予告通知とともに具体的な解雇理由を説明します。
懲戒解雇に関して、就業規則に「弁明の機会を与える」と定めている場合、解雇予告を行う前に本人へ弁明の機会を必ず与えましょう。
また、就業規則の記載がない場合や普通解雇であっても、不当解雇を避けるうえで本人の言い分を聞くことは大切です。
6.解雇手続き
最後に、解雇手続きを進めます。
未払い賃金や退職金の支給、離職票の作成、被保険者資格喪失届の届出などの手続きに加えて、「解雇理由証明書」も準備しましょう。
解雇理由証明書とは、会社が元従業員に対して具体的な解雇理由を説明する書類です。
元従業員が求めた場合のみ、会社は解雇理由証明書を交付する必要があります。
求められた場合に備えて事前に準備するか、あるいは解雇予告通知書とともに手渡しましょう。
問題社員に退職してほしい場合は弁護士への依頼がおすすめ

問題社員にお困りの場合、弁護士へ相談するとさまざまなサポートを受けられます。
これまでの判例では、従業員を解雇する理由は非常に厳しく判断されています。
企業が退職相当と判断しても、裁判所から不当解雇と見なされるリスクは一定程度あります。
弁護士に相談することで、問題社員への対応について最適な方法を考えてもらえます。
正当性の主張に必要な証拠集めや解雇の手続き、問題社員への対応方法もアドバイスされます。
不当解雇や退職の強要と見なされる行為を避け、裁判のリスクを格段に抑えられるでしょう。
万一、問題社員から訴訟された際も、最大限の支援を受けられます。
解雇後に弁護士へ相談しても支援内容が限られるため、できる限り早い段階での依頼がおすすめです。
弁護士を探すならココナラ法律相談へ

問題社員の退職勧奨や解雇に強い弁護士を探すなら、「ココナラ法律相談」をご活用ください。
全国の弁護士の情報が集約されており、企業側の労働・雇用問題を解決に導いてきた多数の弁護士が掲載されています。
サイト上では、地域やお悩みなどの条件から弁護士の絞り込み検索が可能です。
問題社員の対応実績があり、なおかつご自身と相性の良い弁護士をすばやく見つけ出せます。
さらに、ココナラ法律相談は「法律Q&A」も提供しています。
法律Q&Aは、弁護士への相談内容を無料で投稿できるサービスです。
「そもそも弁護士に相談すべき状況なのかわからない」とお悩みであれば、まずはお気軽に法律Q&Aで弁護士へ相談してみてください。
まとめ

問題社員の退職に向けた対応としては、退職勧奨・普通解雇・懲戒解雇の3種類があります。
退職勧奨は従業員の意思による退職になるため、厳しいルールはありません。
しかし、従業員が退職勧奨を拒否した場合、普通解雇または懲戒解雇が選択肢となります。
法律上、労働者の解雇は厳しく制限されており、思いがけず不当解雇とみなされてしまったケースが相次いでいます。特に懲戒解雇は適法性が厳格に判断されるため、仮に行うとしても慎重に判断すべきです。
問題社員にお困りの場合、解雇前の早い段階から弁護士へ相談しましょう。